 【人生態度】に関する教誡/人生訓タイプ 【人生態度】に関する教誡/人生訓タイプ
中国人の普段の会話の中には、人生訓タイプのフレーズが散見され、相手を納得させようとする際によく用いられます。そこから中国人の信奉するさまざまな人生観・人生哲学が垣間見られます。そのいくつかを取り上げてみましょう。
1.踏踏实实地过日子比什么都强。
2.平平安安地过日子才是大福。
3.没病是最大的幸福。
4.人各有志,不能强求。如果她不愿意,你也别勉强她。
5.一切顺其自然,随它去吧。
6.活就得活出个人样儿。
7.谁还能不出点儿差错?
8.谁都有糊涂的时候,饶了他这次吧。
9.他是迫不得已。
10.人生的选择有时身不由己。
★語注 :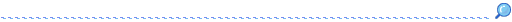
●踏实 tā-shi;【形容詞】堅実である/着実である ●自然 zì-rán;【動詞】成り行く/(人間の力が関与せずに)自然に発展する ●人样儿 rén-yàngr;【名詞】人間らしい姿/一人前の人間 ●糊涂hú-tu;【形容詞】愚かである/ぼんやりしている/間の抜けているさま ●迫不得已 pò bù dé yǐ;【成語】やむを得ずに…する ●身不由己shēn bù yóu jǐ;【成語】体が自分の自由にならない/思い通りに行動できない
★解説 :
▲例文1“踏踏实实地过日子比什么都强。”は「堅実に生きることは何にも勝る」。つまり、浮つかず、地に足を付けてしっかりと日々を堅実に生きること、それは人生において何にも勝ることだ、と説く。
▲例文2“平平安安地过日子才是大福。”は「平穏無事に暮らすこと、これこそが大きな幸せなのです」。▲例文3“没病是最大的幸福。”は「病気をせず、健康に暮らせるのは一番幸せです」。
▲例文4“人各有志,不能强求。如果她不愿意,你也别勉强她。”は「人にはそれぞれ志があるもので、その志に反することを強制するわけにはゆきません。したがって、もしも彼女が望まないならば、無理強いしてはなりません」。ちなみに、人の志・抱負や向上心を重視する観点を示す諺に“人无大志,草木一生(大志なき者の生涯は草木の如し)”があります。
★自然体の生き方?---“一切顺其自然,随它去吧。”
▲例文5“一切顺其自然,随它去吧。”は「すべては自然の成り行きに任せ、その流れに付いてゆこう」。このフレーズは、字面からみて、先入観を持ったり、身構えたりしない自然体の生き方を説くものですが、無我・無心・無欲の境地を示すものと解釈することもできます。これを人間社会に当てはめると、人は他人の干渉を受けることなく、自由かつ自分らしく飄然と生きるべきだと読めます。
それにしても、このフレーズの“自然”はなんだか意味が深そうです。辞書などを調べてまとめると、それは、「宇宙の万物が人間の意志や力の干渉を受けることなく自由に活動し、発展する本来の姿・状態」を指しています。ただ「自由に活動する」といっても、万物にはそれぞれの特性や内部要因が具わっており、その生成・発展・変化・消滅の全過程は一定の法則に支配されているという説があります。そうすると、“顺其自然”とは「自然界の法則や人間社会の発展法則に基づく事物の自律的な営みに順応すること」を指すのではないか、と推論できます。
ここで問題は「順応する」を如何に解釈するかです。消極的な意味の「何でも受動的に容認し、受け入れる」ではなさそうです。むしろ人間の作為と不作為の両方が含まれる点に留意する必要があるように思われます。卑近な事例では、家庭園芸の場合で言うと、草花の成長期に当たる春夏には施肥を行い、休眠期に入る秋冬には施肥を控える育て方があります。これは植物の生命リズムや生長周期に合致しており、“顺其自然”を体現したやり方だと言えます。
その一方で、消極的な解釈も聞かれます。つまり、どうせ人間のできることには限度があり、人間の知恵では解決できないことも多い世の中なので、何事に対しても超然として順応することが肝心だ、そうすれば、人間はいつでも俗世間の喧騒や浮世のシガラミを遠ざけ、心の平和と安穏を保つことができる、という処世態度を指すようです。
ただ、このセリフが人間関係、特に感情面に絡んで使われるときは意味深です。たとえば、恋愛の場合、二人の感情がひどくこじれたとします。そのときに中国人が口にする“一切顺其自然,随它去吧。”はネガティブな発言です。なぜならば、相手とのこじれた関係がさらに冷え込み、ひいては破局を迎えたとしても一向に構わない、という意思表示になっているからです。つまり、わざわざ自分から進んで相手とよりを戻したり、関係修復の手を打ったりはしない。かといって、絶縁宣言もしないままほって置き、恋愛関係が自然消滅するのを容認する、という姿勢を指しています。
こうした言い方や生き方は、一見「無為自然」を旨とする老荘思想が投影しているように見えて、なかなか聞こえはいいのですが、実際は往々にして「無為自然」に名を借りたエゴイズムの表れと疑いたくなる事例が少なくない。要するに、自分が悪くて二人の恋愛感情がこじれたわけではない、だから自分からは折れたくないと身勝手に意地を張っているに過ぎません。行動に出るべき時に出ないそうした後ろ向きの態度は、不作為の怠慢であり、無責任だと非難されるでしょう。
こうしてみると、ことわざや格言も、時と場合によって意味するところが異なるものです。したがって、発言をめぐる情況や背景、および話者の動機・意図などに立ち入って吟味しないと、フレーズの真意や深意を把握できないものだといえましょう。なお、類似表現に“一切随缘(すべては縁に委ねる)”、“一切看缘分(すべては縁がどうなのかに係っている)”があります。
▲例文6“活就得活出个人样儿。”は「生きる以上は、まともな人間になれるように生きるべきだ」。このフレーズの中で、“人样儿”は中国的特色を出しています。“活出个人样儿”は、「この世に人間として生まれたからには、夢を抱き、人生の目標を立て、その実現に向けて努力し、人間社会の中で自尊自立した立派な一員になること」。またそうしないと、人間らしい人間とはいえず、動物並みの存在になってしまうというわけです。古い言い方では「身を立て、名を揚げること」。卑近な言葉で言えば、「俺は仕事で実績を上げ、出世するぞ」、「一人前の人間になるよう頑張らなくちゃ」などと決意をアピールしたり、またそうするよう人に忠告したりする言い方になっています。
▲例文7“谁还能不出点儿差错?”は「誰でも間違いを起こすものです」。原文は反語文→「少しもミスしない人間なんていますか?」
▲例文8“谁都有糊涂的时候,饶了他这次吧。”は「誰でもバカなマネをしてしまうことはあるものです。今回は彼を見逃そう」。
▲例文9“他是迫不得已。”は「彼はやむにやまれなかったのです」。追い込まれた末に取った彼の行動には、同情すべき点があると弁護するような言い方。
▲例文10“人生的选择有时身不由己。”は「人生における選択は、思い通りにならない時もあるものだ」。つまり、私たちは人生行路の行く先々でさまざまな選択を行うが、時にはよいと思ってその道を行こうとしても、シガラミなどによって意に反する選択をしてしまうこともあるものだ。
【人生態度】に関する格言・ことわざ・成語など
●家和万事兴 ---「家庭円満になれば、万事うまくゆく」
●有活力才叫生活----「活力あっての生活です」/「活」力に欠けたら、生「活」とは言えない。
●以和为贵,和而不同---「和をもって貴しと為し、和して同じず」
●人生得一知己足矣!---「人生は一人の知己を得れば、それで充分満足すべきなのです!」
●有梦想的人是幸福的---「夢を持つ人は幸せです」
●梦在前方,路在脚下---「夢は彼方に、道は足元にある」
●有梦不怕路远---「夢があれば、道が遠くても厭わない」
●前途是光明的,道路是曲折的---「前途は明るく、道は曲がりくねっている」
●车到山前必有路---「行く手に山が立ちふさがっても、そこに道はおのずと開けるものだ」/「行き詰まっても、必ず解決する方法があるものだ」/「窮すれば通ず」/「物事は転機を伴うものだ」
●天下无难事,只怕有心人---「この世に難事はなし、志ある人を恐れるのみ」/「この世のどんな難しい事も志高き人には敵わないものだ」。
●天下没有过不去的坎儿---「この世に乗り越えられない苦境はない」→第44話“有我在,就没有过不去的火焰山”参照
●有志者事竟成---「 志があれば、最後には成し遂げられる」
●千里之行始于足下---「千里の道も一歩から/千里の旅も足元から始まる」
●一份汗水一份收获---「苦労して汗を流せば、それだけの収穫が得られるものだ」/「努力しただけ報われる」
●书山有路勤为径,学海无边苦作舟---「知識の高峰に登る道は勤勉、学問の大海を渡る船は努力」
●身有一技长,不愁隔夜粮---「一芸に秀でれば、明日の糧に困らない」/「芸は身を助ける」
●世无完人---「この世に完全な人間は存在しない」
●人生一世岂能事事如意---「人生が一生涯、万事意のままになることなど有りえましょうか?」/「人生はままならない」
●智者千虑必有一失---「如何に知恵のある人でも、千に一つの誤りはあるものだ」/「弘法にも筆の誤り」
●比上不足比下有余---「上に比べれば及ばないが、下に比べればましである」/「ほどほどである」
●自己种下的恶果要自己尝---「自分で育てた悪しき果実は自分で味わうべきだ」/「自ら招いた悪い結果は自ら背負わなければならない」
●吃人家的嘴软,拿人家的手短---「人に食べさせてもらったり、人から物をもらったりすると、相手に頭が上がらなくなる」
●吃软不吃硬---「相手が下手に出ると受け入れるが、高飛車に出ると反発する」
次話では、今話にひきつづき【中国流の説得法/物事に対する処理態度について】をテーマに取り上げ、関連する日常フレーズと諺をたくさん紹介したいと思います。
|
【人生態度】に関する教誡/人生訓タイプ