 物事に対する処理態度・方法に関する教誡・説得フレーズ 物事に対する処理態度・方法に関する教誡・説得フレーズ
「“慢慢来吧,总有办法的。”⇒じっくり考えて対処しよう、何か良い方法があるはずだ」。これは、昔から中国人がよく口にする慣用句の一つです。つまり「(問題にぶつかっても)慌てず急がす、じっくりと腰を落ち着けてあれこれと考慮し、対処すれば、解決する良い方法や対策が見つかるものだ」と、難題を前にして慌てる人をなだめたり、途方に暮れる人を励ましたりする時に用いられます。中国といえば、広大な国土と悠久の歴史文化が大きな特色ですが、そのような国柄と風土が育んできた、おおらかな国民性を表す慣用句だといえましょう。
このセリフは、以前に取り上げた“车到山前必有路(窮すれば通ず/案ずるより産むが易し)【第73話参照】”に類似した人生態度・暮らしの知恵を反映しており、人生楽観主義の色彩が強い。逆に“坐不住,等不起,慢不得,只争朝夕(じっとして居られない、待っている余裕はない、ノロノロしていては大変なことになる、ただ一刻を争うのみだ)”はその正反対で、喫緊の重要課題だから、早急に取り組む必要があると力説するときの言い方です。
ちなみに、中国市場に初めて進出した当時のトヨタは、販路開拓のためにあるキャッチコピーを考案して宣伝攻勢をかけ、奏功した経緯があります。じつはそれが“车到山前必有路,有路必有丰田车(窮すれば通ず、通ずる道にはトヨタ車がある)”でした。中国人なら皆知っている諺を商いの宣伝文句として巧みに利用した点は、ある意味において「人の褌で相撲を取る」スタイルですが、市場経済ルールに適った商魂たくましいやり方だと中国商人も舌を巻くほどでした。
★「人の褌で相撲を取る」=“借花献佛”???
ところで、「人の褌で相撲を取る」、これはいかにも日本的で、日本語らしい表現だと思いますが、市販の主だった日中辞典は大抵これを“借花献佛”と訳しています。両者を引き比べると、「褌」と「花」、「相撲を取る」と「仏前に供える」がそれぞれ対応しています。でも、なんだか妙に落差が大きいので、違和感を覚える人は少なくないと思う。
たしかに“借花献佛”の由来は、字面解釈の通り「他人の花を借りて、仏前にお供えすること」です。私の勝手な想像では、たぶん「手ぶらで寺の前を通りかかった信者が、素通りするのは仏様に義理を欠くと思い、供花を手に入れようとしたが果たせず、急遽、身辺の参拝客から少し分けてもらい仏前に供えたこと」を指しているのだろうと思います。それが今の中国では移り変わって、「人から贈られた物を贈り物に利用すること」を比喩的に言う場合が多い。例えば、“请不要客气,这些东西都是朋友送的,我只不过是借花献佛罢了。(どうかご遠慮なく受け取ってください。じつはこれらの品はみな友人からの贈り物でして、私はただこうして利用させてもらっただけのことですから…【应用汉语词典】から引用)”
つまり“借花献佛”は「事のついでに義理を尽くす」とか「貰い物で義理を済ます」意味が付いて回る点がポイントになっています。したがって、他人の物を利用して、自分に都合のよいことをしたり、自己の利益を図ったりする点では、「人の褌…」と意味は一致しているわけです。しかし、「人の褌…」には「事のついでに義理を尽くす」意味は全然ないので、両者の違いもまた明らかです。しかも「相撲取りの褌」はいわば一身専属的なもので、いわゆる「贈答品」でもないし、日常の「貰い物」でもないはずです。その意味において、両者の対訳関係は果たして成立するのか、大きな疑問が残ります。
それにしても、この対訳を見比べると、俗でデリケートな「褌」と厳かな「供花」、さらに競技の「相撲を取る」に対する仏事の「お供えする」、これら両者それぞれの落差はいかにも大き過ぎます。仮にこの差を縮める試みとして、「褌」をあの華麗な「化粧回し」に変え、また「相撲を取る」を「奉納相撲に登場する」に変えたらどうなるのか、と想像してみました。例えば「人の化粧回しで奉納相撲に登場する/奉納土俵入り」と言えば、一見風雅な“借花献佛”の原義とかなり近い意味、似通った雰囲気になると思いますが…。
なぜなら、奉納相撲といえば、天下泰平・五穀豊穣を願い、神前で力と技を捧げる神事ですから、仏前のお供えと似通ってくるではありませんか。ただ、現実問題として、厳かな奉納土俵入りを行う横綱が、果たしてちゃっかり他人の化粧回しを使うものだろうか?いや、いや、まずありえない!となると、語句の入れ替えはそもそも無理な話で、ここはやはり、「人の褌で相撲を取る」というほかはありません。とすると、「人の褌」には何か深い意味があるのでしょうか?
少し調べてみたら、一説によると、「相撲取りの褌/まわし」は「力士のたゆまぬ稽古、精進のシンボルであり、とうてい安易に貸し借りできるものではない」という。また「まわしを締め込む時は、心身共に緊張させ、邪念・汚心を去り、清明・明朗の心境を以て締め込まなければならない」と言われます。
もしそうであるならば、人の褌を借りる行為自体が大きな問題になります。なぜならば、強い兄弟子の「胸」を借りて稽古に励むことは無論よいとしても、果たして兄弟子の大事な「褌」まで安易に借りて土俵に上れるものなのか、大いに疑問です。「礼・義・恥」を重んじる相撲道の道徳規範から言えば、まずありえないだろうと思います。やや極論ですが、「褌は男の魂」だと主張する日本人もいるくらいですから。
また別の解釈によると、「人の褌で相撲を取る」という諺には、自分で努力せず、安易に他人に頼り、他人を利用する厚かましさに対する軽蔑の意味が込められているという。それならば、中国語の“借鸡生蛋(借りた鶏に卵を産ませる)”“借壳上市(ヤドカリ式の株式上場)”のほうが適訳ではないかと思います。
こうしてみると、何気なく使っている「人の褌…」もなかなか奥が深いものだと感じます。日本の歴史文化や風土・人情などに関する知識がないと、深く理解することは難しい。同じく、中国語の“借花献佛”の故事来歴にも諸説があり、興味をそそられますが、ここでは紙幅の関係で割愛させて頂きます。
さて、話がいろいろと脱線し、ちょっと混線してしまいましたので、閑話もここまでにして、今話の眼目である「物事に対する処理態度・方法に関する教誡・説得フレーズ」を取り上げてみたい。
1.慢慢来吧,总有办法的。
2.让我再想想办法,也许还有转机。
3.这里面有很多复杂的原因。
4.解决这种问题总得有一个过程嘛,别着急。
5.现在还没到最后呢。
6.等下一次机会吧。
★語注 :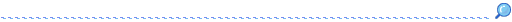
●总zǒng;【副詞】結局は/最後には/所詮/どのみち
★解説 :
▲例文1“慢慢来吧,总有办法的。”は「じっくり考えて対処しよう、何か良い方法があるはずだ」。ここでの“来”は“想/考虑/做/对付”などの代役。
▲例文2“让我再想想办法,也许还有转机。”は「もっとほかに方法はないものか、よく考えさせてください。まだ挽回のチャンスがあるかもしれませんよ」。
▲例文3“这里面有很多复杂的原因。”は「これには多くの複雑な原因が含まれています」。つまり難解な問題は大抵、幾つもの内在条件や内部要因が絡まって、複雑な矛盾を作り出した結果であるとの考えを示しています。
▲例文4“解决这种问题总得有一个过程嘛,别着急。”は「この種の問題を解決するためには、どうしても筋道や手順を踏みながら進めて行く必要がありますからね、焦らないでね」。つまり、複雑化した問題なので、一足飛びに解決するのはそもそも無理があるという主張。
▲例文5“现在还没到最后呢。”は「現時点で(この事は)まだ終わったわけではありませんよ」。つまり「(この段階で)結論を急ぐのは時期尚早であり、諦めたりすることもないですよ」などと相手の注意を喚起したり、励ましたりする言い方です。
▲例文6“等下一次机会吧。”は「次の機会を待ちましょう」。今回は条件が合わないから見送ろうとか、失敗してしまったけれど、次の機会に挽回を図ろうという言い方です。
次話では、物事を処理する際の中国人の「複眼的思考方法」や「バランス感覚」を示すフレーズを主として取り上げます。乞う、御期待。
|
物事に対する処理態度・方法に関する教誡・説得フレーズ